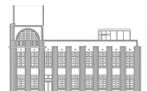名誉館長のつぶや記
名誉館長のつぶや記78 水に映る赤い火の粉
つぶや記 78
水に映る赤い火の粉
Kさんは勢いよく燃え残りの薪を湖水へ遠く抛った。薪は赤い火の粉を散らしながら飛んで行った。それが、水に映って、水の中でも赤い火の粉を散らした薪が飛んで行く。上と下と、同じ弧を描いて水面で結びつくと同時に、ジュッと消えてしまう。ーーーーー
志賀直哉の短編『焚火』 (新仮名づかいに変更)の一節です。夕闇せまる山中湖畔から空に投げ上げた燃え残りの薪が、彗星のような火の粉の尾をひきながら、放物線を描いてゆるやかに落ちてゆく。湖水に映った同じ光の円弧の先端が湖面で交わると同時にジュッと消えてゆく幻想的な情景は、前後の文脈を省略していても、充分に想像をかきたてられます。推敲をかさね、削りに削った志賀直哉の文章見本というべき例文です。
死期が近づいたころの太宰治は、志賀文学を「植木職人」の芸にすぎないなどと毒づきました。修飾語のない平明な文節、センテンスの長短、その配列によって、自然に色づけされた文章に仕上げて行く。たとえばモノクロ写真を天然色にして見せる文章技法は魔術的でさえあります。初心のころ、わたくしは志賀直哉に心酔して、『焚火』を繰り返し書写したものでした。
こんど田中絹代ぶんか館でひらいた文章教室で、わたくしは「文章はこうして書きますというような話は出来ません」と断って、あれこれと雑話めいたことを喋りましたが、少しは看板通り「文章作法」的な内容も盛り込んでおこうと思い、冒頭に掲げた志賀直哉の『焚火』の一節を書き写してもらうことにしました。私の長話より、よほど役に立ったに違いありません。
(古川 薫)