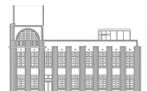名誉館長のつぶや記
名誉館長のつぶや記220 『花燃ゆ』終末の輝き
つぶや記 220
『花燃ゆ』終末の輝き
NHK大河ドラマ『花燃ゆ』が、締めくくりのクライマックスを迎えています。このドラマは滑り出しのころ視聴率の低調がいわれました。わたくしなども史実との違和感を覚えて、素直に鑑賞できずにいたのですが、やはり目が離せず毎日曜日の夜8時にはテレビの前に坐り続けました。
そのうち、あることに気付きました。それは幕政の土台が腐食し、外圧に揺らぎはじめた世紀末の日本に生きた若者が、祖国の未来を拓くために戦う姿を映し出そうとするドラマ作りの迫力を感じてきたということです。
視聴率云々に惑わず、ひたすら押し出してゆく制作陣営の気力といってもよいでしょう。昭和の15年戦争の不幸を歩みだす以前の日本が辿った明治維新の歴史を正視しているのだという実感が、次第に伝わってきたのです。
その維新史が敷いた軌道をどこで誤ったかを考えさせる史劇でもありました。あれが違う、これが違うと重箱の隅をつつくばかりで、全体として把握しているドラマの筋道を受け入れようとしない狭量さに気づきました。
とにかく舞台が群馬に移ってから、がぜん面白くなったのは、楫取素彦という人物の事績をあまり知らないことにもよるのでしょう。妙に予備知識のない白紙の状態では、重箱の隅をつつきようもないわけです。韓流史劇が面白いのと同様です。
中央の維新政府から派遣された官僚が、さまざまな抵抗を潜り抜け、排除して改革に取り組んでゆくストーリーは実に興味津々です。
素彦の妻つまり吉田松陰の妹寿が、アメリカに出ていく若者に、松陰遺愛の刀剣を贈ったのは史実で、兄の見果てぬ夢を託す場面は感動的でした。
ドラマはドラマですから、史劇を面白く観るためには、なまじ郷土史家流の詳細な知識は横に置くことが大事だということを悟りました。
(古川 薫)